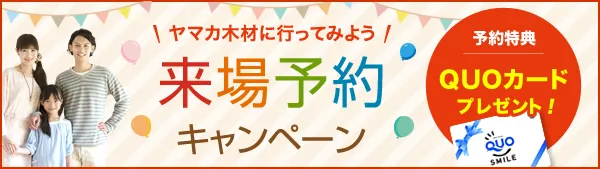2025.05.30 お役立ち情報
土地購入の注意点は?後悔しないためのポイントやチェックリストも紹介

土地の購入は、人生の中で大きな買い物の1つです。気軽に購入できるものではないため、事前に注意点を確認しておき、失敗のない土地選びを意識することが重要です。
この記事では、土地の購入時に押さえておきたい注意点について解説します。後悔しないためのポイントやチェックリストも紹介するので、土地探しを始める人はぜひ参考にしてください。
【この記事でわかること】
- 土地購入における注意点
- 土地購入において注意すべき土地の特徴
- 土地購入で後悔しないためのポイント
- 土地購入で役立つチェックリスト
目次
まずは土地を購入する前の注意点を押さえよう
土地購入時には予算やエリア、面積の検討に多くの時間を費やすべきですが、購入を検討している土地にどのような法令制限や制約があるのかも同時に知っておく必要があります。
土地に関する法令制限と制約について、主に次の2点があります。
- 建物の種類や性能への規制
- 土地によって変わる家の規模や形の制約
建物の種類や性能への規制
検討している土地が、都市計画法に基づく都市計画区域に該当している場合、建築して良い建物の種類が制限されることがあります。
都市計画区域には用途地域と呼ばれる13種類のエリアが割り当てられ、それぞれ建築できる建物が厳密に分けられます。
たとえば、第一種低層住居専用地域では1階を店舗とした3階建て住宅を建築することは難しく、経営する店舗の種類によっては建築許可が降りません。主に、小規模なお店や事務所をかねた住宅、小中学校などを建てられます。
また、工業専用地域ではどのような工場でも建てられますが、住宅やお店、学校、病院、ホテルなどは原則不可能です。
このように、エリアによってどのような建築物を建てられるのかをあらかじめ検討しておく必要があります。
土地によって変わる家の規模や形の制約
建築物を建築する場合、都市計画法に加えて建築基準法と道路法を遵守する必要があります。
たとえば、建築面積の敷地面積に対する割合を示す建ぺい率や、敷地面積に対する延べ床面積の割合を制限する容積率などが建築基準法の制限にあたります。
また、前面道路を4m以上確保し2m以上接道しなければならないという「接道義務」も建築基準法の「集団規定」により定められています。
エリアによってはさまざまな法令制限があるので、検討している土地にどのような制限があるのか、あらかじめハウスメーカー担当者に確認しておくことが重要です。
土地購入における注意点5選
ここでは、土地購入をする際に最低限チェックしておくべき注意点を5つ解説します。
- 用途地域を確認する
- 地盤が強固であるか確認する
- 接道義務を果たしているか確認する
- 隣地との境界線が明確か確認する
- 周辺環境が良好か確認する
用途地域を確認する
前述した用途地域は、建築物の建築許可を取得する難易度に大きく影響します。特に、店舗兼住宅を検討する場合は、必ず許可要件を満たすかどうかチェックしておきましょう。
確認する具体的な方法として、以下が挙げられます。
- 契約前に不動産会社から用途地域の種類を確認する
- 用途地域で建築可能な建物の種類や建ぺい率、容積率、高さなどの建築制限を確認
用途地域を確認せずに土地を購入してしまうと、希望する建物を建てられないリスクがあるため、入念に調べてから取得しましょう。
地盤が強固であるか確認する
地盤が強固でない場合は、改良工事が必要となります。
比較的安価に対応できる表層改良で済む場合は問題ありませんが、場合によってはソイルセメントや鋼管杭といった大規模改良工事が必要になる場合があります。
地盤が強固であるかを専門家に確認する方法は、主に以下のとおりです。
- スウェーデン式サウンディング試験
- ボーリング調査 など
スウェーデン式サウンディング試験は、一般的な住宅の場合に用いられることが多い調査方法で、費用は5万円程度と手頃です。
マンションや規模の大きい建物の場合にはボーリング調査を行うのが適しており、費用は25万円から30万円ほどかかります。
接道義務を果たしているか確認する
接道義務とは、敷地が4m以上の道路に2m以上接していることです。延長敷地と呼ばれる形状の土地は、延長部分の長さが接道幅によって変わるため注意が必要です。
接道義務を果たしているか確認する方法として、以下が挙げられます。
- 市区町村の建築指導課などで確認する
- 不動産会社に問い合わせる
建築基準法上の道路であるかは、市区町村の建築指導課に備えられている道路図面で確認できます。
宅建業者が土地の売買を仲介する際には、買主に接道条件を説明する義務があるため、不動産会社に問い合わせるのも良いでしょう。
隣地との境界線が明確か確認する
境界線が明確かどうかを目視で確認することは前提ですが、境界杭の有無についても重要です。
境界杭がない場合は売主に確定測量をおこなってもらい、杭を設置するのが一般的です。
しかし、中には測量で隣地と売主が揉め、険悪なムードで引渡しを受けることがあります。そのような事態を避けるためにも、境界線と境界杭が明確になっていることが重要です。
隣地との境界線を確認する方法は、主に以下のとおりです。
- 法務局で土地情報を調べる
- 測量士または土地家屋調査士に測量してもらう
- 市役所で道路との境界線を調べる
法務局には、土地や建物などの不動産情報が登記されており、誰でも調べることが可能です。測量士や土地家屋調査士などの専門家に依頼すると正確な境界線が明らかになります。
なお、市役所の道路管理課や建築指導課でも、道路との境界線を調べられます。
周辺環境が良好か確認する
周辺環境は土地の周りだけでなく、少なくとも3ブロック先までは確認するようにしましょう。また、夜間と昼間の状況を知っておくことも重要です。
土地を見学する際には土日祝であることも多いため、平日の状況も購入前にはチェックしておきましょう。
周辺環境が良好か確認する方法は以下のとおりです。
- 現地調査を徹底的に行う
- 行政情報を確認する
- インターネットを活用する など
時間帯を変えて複数回訪問し、スーパーや病院など生活関連施設が近くにあるかを現地で確認します。自治体の公式ホームページでどのようなまちづくりに取り組んでいるかなどをチェックするのも良い方法です。
Googleマップや地域に関する口コミサイトなどで、エリアの評判・口コミについて知っておくこともおすすめします。
土地購入において注意すべき土地の特徴
購入を検討している土地にリスクがあるかどうかを把握するためにも、注意すべき土地の特徴を知っておく必要があります。
- 隣地との高低差がある
- 土地の形が歪んでいる
- 土地の前に消火栓が設置されている
一般的に、上記3点の土地は購入後のリスクがあるため、注意が必要です。
隣地との高低差
隣地との高低差によるリスクは日当たりが考えられますが、隣地が2m以上高いケースや1m以上低いケースではガケ条例が適用され、建築がそのままではできません。
ガケ条例を回避するために建築面積を制限したり、擁壁を組んだりなどの対応が必要です。
土地の形
土地はキレイな整形地だけでなく、ひし形や凸型といったさまざまな形状があります。いびつな形の土地は建築できるもののデッドスペースが多く、使っていない土地が多くなります。
そのような土地に家を建築した場合、デッドスペースの固定資産税を無駄に支払い続けることになるため、注意が必要です。
消火栓の設置
土地の前面にはガードレールやカーブミラー、電柱といった建造物が設置されている場合がありますが、消火栓が設置されている場合は注意が必要です。先に挙げた3つの建造物は移設可能なものです。
ただし、消火栓は原則移設できません。そのため、消火栓にぶつけないよう駐車する必要があり、さらには有事の際には目の前に消防車が停車する場所となってしまいます。
土地購入で後悔しないためのポイント
土地購入で後悔しないためのポイントとして、以下が挙げられます。
- 購入前に価格相場を調べておく
- 希望条件の優先順位を決めておく
- 実際に現地を複数回訪問する
購入前に価格相場を調べておく
まずは、土地購入前に価格相場について調べておくことが重要です。
価格相場を調べておけば、提示されている売却価格が適正であるかを確認できます。相場より高い場合は価格交渉を行う、あるいは購入を見送るなど的確な行動を取れるでしょう。
相場の価格を知るには、国土交通省が運営する不動産情報ライブラリや、不動産情報ポータルサイトなどで、購入したい物件が所在するエリアの売却価格を調べます。
希望条件の優先順位を決めておく
土地を購入する際は希望条件の優先順位を決めておくことも重要なポイントです。
全ての希望条件を満たすことは難しいので、譲れない条件を優先的に決めておきます。何を最も重視するかを明確にすることで、物件を選ぶ際の判断軸となるでしょう。
不動産会社に土地探しを依頼するときは、優先順位を決めておくとニーズに合った物件を紹介してもらえる確率が高まります。
優先順位を決める際は家族全員で話し合い、将来のライフプランも見据えたうえで判断するようにしましょう。
実際に現地を複数回訪問する
土地探しにおいては、実際に現地を複数回訪問することも欠かせません。一度見ただけや、インターネットの情報だけでは現地の様子や周辺環境の細部までは把握できないからです。
有効な方法として、日中と夜間の時間帯に分けて下調べすると良いでしょう。可能であれば、季節ごとの変化も把握しておくのが望ましいといえます。
近隣住民の生活音や街の雰囲気など、現地でないとわからない情報も確認しましょう。
土地購入で役立つチェックリスト
ここでは、土地購入に役立つチェックリストとして、現地確認・物件情報確認・法規制の確認に分けてまとめました。
【現地確認】
| 確認事項 | 確認する内容 |
| 立地・日当たり・景観 | ● 最寄り駅からの距離
● 日当たりや風通しに問題ないか ● 治安が良く暮らしやすい環境であるか |
| 近隣の建築計画 | ● 周辺に高層建築物や騒音が懸念される建築物が建つ計画がないか |
| 学校・幼稚園・スーパー・病院・公園までの距離 | ● 子育てしやすい環境であるか
● 生活利便性の高い施設が周辺にあるか |
| 騒音・振動・におい | ● 前面道路からの振動の有無
● 周辺のにおい |
現地確認では、最寄り駅からの距離や日当たり・風通しなどが重要確認事項です。子育て世帯の場合は、周辺に学校や幼稚園、スーパーなど子育てしやすい環境であるかも確認しましょう。
【物件情報確認】
| 確認事項 | 確認する内容 |
| 価格 | ● 土地購入価格 |
| 土地の面積・形状・境界 | ● 土地の広さ
● 土地の形状(整形地・不整形地) ● 隣地との境界線 |
| 土地の高低差・災害リスク | ● 道路と同じ高さであるか
● 過去に起きた災害 |
| 地盤 | ● 地盤が弱くないか |
| インフラ | ● 上下水道・ガス・電気などインフラ設備の引き込み状況 |
物件情報の確認では、土地購入価格が予算内であるかが大切なポイントです。土地の面積・形状・高低差なども目でチェックして、家を建てても問題ないかを確認しましょう。
【法規制の確認】
| 確認事項 | 確認する内容 |
| 建築基準法・都市計画法 | ・接道状況の確認(建築基準法で定められた道路に2m以上接しているか)
・用途地域による建築物の用途制限 ・計画道路の有無 |
家を建てる場合、敷地が建築基準法で定められた道路に2m以上接しているかが重要なポイントです。希望する建物が建てられる用途地域を選びましょう。
土地購入の注意点に関するよくある質問
ここでは、土地購入に関するよくある質問を紹介します。
- 待った方が良い土地を買える?
- 土地購入で後悔して立ち直れないときはどうすればいい?
- 買わない方がいい土地は存在する?
待った方が良い土地を買える?
車や時計であれば気に入った品をいつでも購入することができ、一点物の洋服でも一旦取り置きしてもらうことで他の人に購入されないようにすることができます。
ただし、不動産は全て世界で1つの一品物となっており、さらには仮押さえができません。そのため、「この土地も良いけどもっと良い土地が出るかもしれない」という考え方は危険です。
待つことで良い土地が出たとしても、比較するために保留にしておいた土地はすでに他の人が購入しているでしょう。気になる点がない土地と出会った場合は、なるべく早く検討し購入の判断をすることをおすすめします。
土地購入で後悔して立ち直れないときはどうすればいい?
購入した土地がどうしても気に入らない場合、早めに売却することをおすすめします。
高くなってから売ることもできますが、市場価格の変化は誰にも分からず、固定資産税という維持費を支払い続ける必要があります。
気に入らない立地に住み続けるということもストレスになるため、早期売却をすることで新しく土地を探すことが賢明です。
買わない方がいい土地は存在する?
一概には言い切れませんが、買わない方がいいとされる土地は一定数存在します。例として、以下のような土地は購入に注意が必要です。
- 再建築不可物件が建っていたなど法的な問題がある土地
- 地盤や自然災害のリスクが高い土地
- 周辺環境に問題がある土地 など
再建築不可物件を解体した土地には建築できないため、購入しても家などを建てることはできません。
地盤が弱い土地は、地盤改良をする必要があり、費用がかかります。浸水想定区域や土砂災害警戒区域など、自然災害のリスクが高い土地も、できれば購入の判断を見直すことをおすすめします。
なお、治安が悪かったり、騒音がひどかったりする場所にある土地も、人によっては快適に暮らせないおそれがあるでしょう。
土地購入における注意点を押さえて理想の土地を手に入れよう
土地を購入する際には、土地の特徴や用途地域の種類、周辺環境が良好であるかなど入念にリサーチをしてから判断することが必要です。
希望条件を全て満たせる土地はないため、譲れない条件と妥協できる条件を家族で話し合い、優先順位を明確にしてから選びましょう。
異なる時間帯で複数回訪問し、日あたりや風通し、治安の状況などを確認することが望ましいといえます。
ヤマカ木材では、愛知県や岐阜県を中心に、自然素材にこだわった家づくりをご提案しています。土地購入についても、アドバイザーがお客様に寄り添いながらご相談を承ります。